どーも直行直帰の店主です。
私のプロフィールです。
適宜ご参照ください。
20人前のビリヤニを提供できる場が整った
長らく通っていたブラジリアン柔術のジムを卒業することになり、
最後ということもあってジムの会員様向けにビリヤニを振る舞う会を設けることになった。
2021年7月24日㈯の予定
想定人数は20人分
米の重量に換算すると1.5kg分と言ったところか。
容量17リットルの鍋も購入済み
もちろん底厚で焦げ付きにくいアルミ鍋をチョイス。
以前から次の間借り出店も睨んで20名程にビリヤニが提供できる場が欲しいと思っていたので、願ってもいないチャンスだ。
20名分のビリヤニはさすがに妻と私ともうすぐ2歳の娘では消費しきれないので、人に食べてもらう場がないと調理の練習も出来ない。
そんな中出会ったとあるレシピ

本番まで時間もあまりない中レシピ固めに取り掛かっているところだが、
そんな中某有名雑誌にて、今界隈で最も話題のシェフが作る本気ビリヤニのレシピが掲載されるとのことから、早速購入して調理してみた。
内容は今までどのメディアにも落ちていないような(私にとっては)斬新な調理法ばかりで、まさに目からウロコってやつ。
インド人の調理法ともまた違う。
例えばパッキ式ビリヤニではグレイビーを調理する前に肉を素揚げする等、
とにかく手間がかかるレシピで本気度がビシビシ伝わってくる。
湯取り用の水2Lに塩60g!?
レシピを丁寧に守りつつ調理を進めていたところ、湯取りでバスマティライスを茹でる際の調理工程に気になる記述を発見。
「バスマティライスは塩分量3%の茹で湯で5分下茹でをしてから…(以下省略)」

塩分量3%の茹で湯だと!?
なかなかイメージしづらいと思われるのでレシピに表すと以下の通り。
- バスマティライス 300g
- 水 2L
- 塩 60グラム(正確には某メーカーの粗塩)
塩60グラムと言えばサラサラした精製塩の場合、大さじ3強はある。
今までのビリヤニ作りでは茹で湯には小さじ1の塩しか入れていなかったので、ざっと10倍の塩分量。
いやいや、界王拳じゃねーぞ…。
己の目を疑ったが、間違いなく塩は60グラムとあるのでレシピに従うことに…。
ベストな米の炊き具合のヒントをレシピに求めていたので、すがるような気持ちもあった。

もしかしたら塩分量がベストな米の炊け具合の鍵かもしれない…
銀河系で一番しょっぱいビリヤニの完成

やはりメチャメチャしょっぱいビリヤニだった…。
いや、むしろ塩そのものを食っているような感覚すらあった。
ビリヤニのコメ単体ではとても食べられない程(むしろ健康を害すと思われるほど)なので、残りは白米と1:1で食べている。
それでもちょっと塩辛いけど…。
私は普通のサラサラとした精製塩を使ったが、レシピにはとあるメーカーの粗塩を使うとあった。
塩の違いがこの超絶怒涛のしょっぱさの原因という可能性もある。
Twitterでのご指摘によると、レシピ記載の粗塩は水分を含んでおり、同重量でも塩分は精製塩に対して80%程しかないらしい。
「なんだそれが原因か」と一瞬思いたくもなるが、60グラムの80%でも48グラムなので、大さじ2.5はある。
うーん、ちょっと私にとっては多すぎるかなぁ…。
お断りしておくと、レシピ批判をするつもりは毛頭ない。
塩加減の好みなんて人それぞれだし、使ってる塩が違う以上同じ塩分量でも味の違いが出る可能性は大いにあるのだから…。
このことから得られた教訓
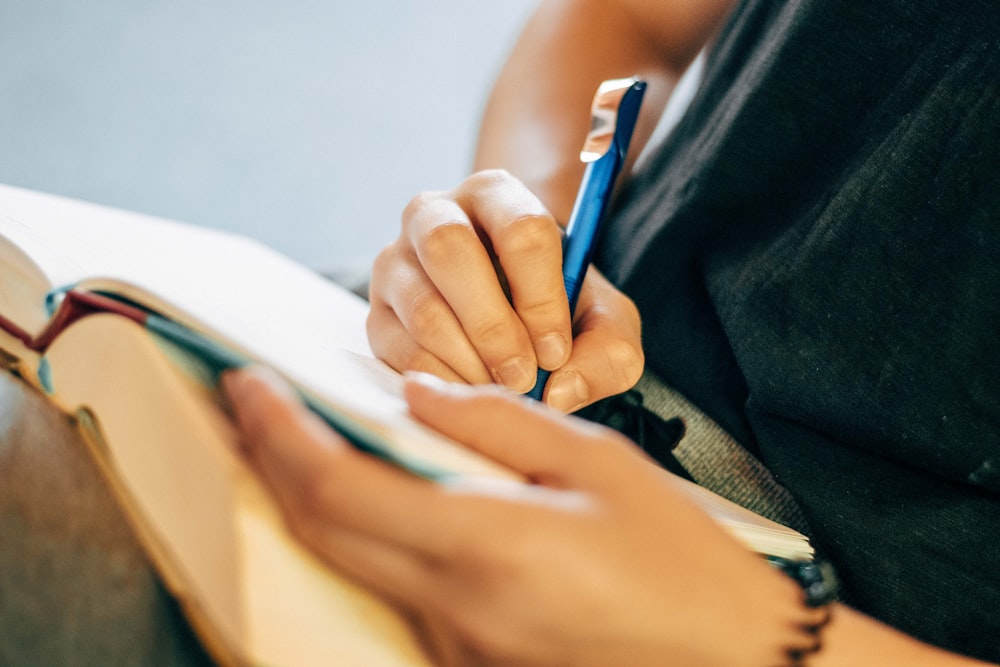
とあるブログで「水分量と塩分さえバチッと決まれば、どの料理も大体美味しくなる」という記述があったが、私もそのとおりだと思う。
それぐらい塩分量ってのは大事だし、同時に個人によって好みの差が出やすい。
濃い味が好きな人もいれば、薄味好きもいる。
居酒屋メニューの塩分量が多めなのはビールを売るための必然だ。
私自身レシピに忠実になった結果塩分量で失敗したのはこれが二度目なので、
もう同じ轍は踏むまいと固く誓ったところである。
他人レシピの塩分量で「おやっ?」と思ったら迷わず自分の感覚に従ったほうが良い。
副産物的な気づきも…
それともう1点気づいたことがある。
ビリヤニを炊いているとき、スパイスの香りがいつもより立っているような気がした。
(その分塩の香りも強めではあったが…)
塩が足りないとスパイスの香りも立たないというのはよく言われるところではあるが、
致死量寸前の塩を投入してしまったことでこんなことにも気づけたのであった。
しかし個人的にはビリヤニはやや薄味が美味しいと思っているので、
一概に塩分量を多くすることは今後もない。
まとめ
今回の記事はこれが言いたいがためにペンを取った次第である。
レシピ記載の塩分量はあなた好みの塩加減ではない!
違和感を感じたら迷わず修正を!
重ねて申し上げるが、決してレシピ批判がしたいわけではない。
ジムのビリヤニ会まであと2週間程度。
時間はあまりない。
今日はこのへんで。
ではまた!

インド料理ランキング
↑応援お願いします!



コメント